〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-2-15第3朝日ビル7階
(小伝馬町駅・人形町駅徒歩5分、三越前駅徒歩7分、新日本橋駅徒歩6分)
インボイス制度を知ろう!
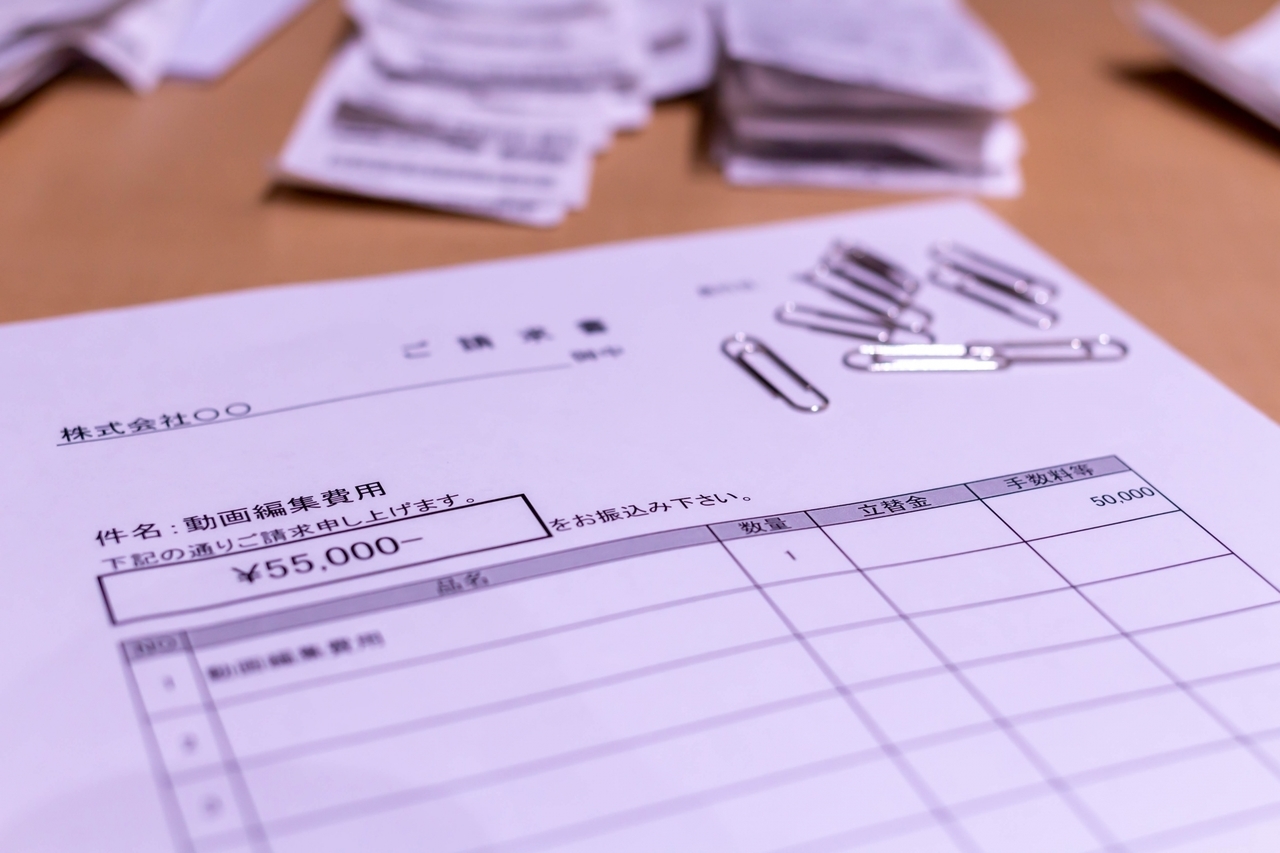
インボイスがないと仕入税額控除が
受けれなくなります。
令和5年(2023年)10月1日より消費税のルール、インボイス制度が導入される予定です。現在は改正の経過措置期間中ですので消費税に影響は出ていませんが、令和5年(2023年)10月1日以降には実際の税額に影響が出るほか、請求書上に事業者の番号(適格事業者番号)を記載する必要が出てきます。
インボイス制度を少しでもわかりやすく、そして理解していただくためのお役立ちページとなっております。
・インボイス制度とは?
・インボイス制度の役割
・インボイスでなければ仕入税額控除できな!?
・インボイスの登録制度について
・インボイス制度ページのご紹介
インボイス制度とは?
インボイス制度とは、登録をした課税事業者(税務署に消費税を納めている業者)のみが法的効力のある『インボイス(適格請求書)』を発行できるという新しい制度です。制度の正式名称は『適格請求書等保存式』といいます。インボイス制度での最大のポイントは、『登録できるのは課税事業者のみ』、『登録をした事業者は必ず消費税の申告をしなければならない』ということです。
適格請求書発行事業者になるためには、法人や個人事業主が税務署に登録申請をします。
インボイス制度導入日に間に合わせるためには、令和5年(2023年)3月31日までに申請書の提出が必要です。
インボイス制度の役割
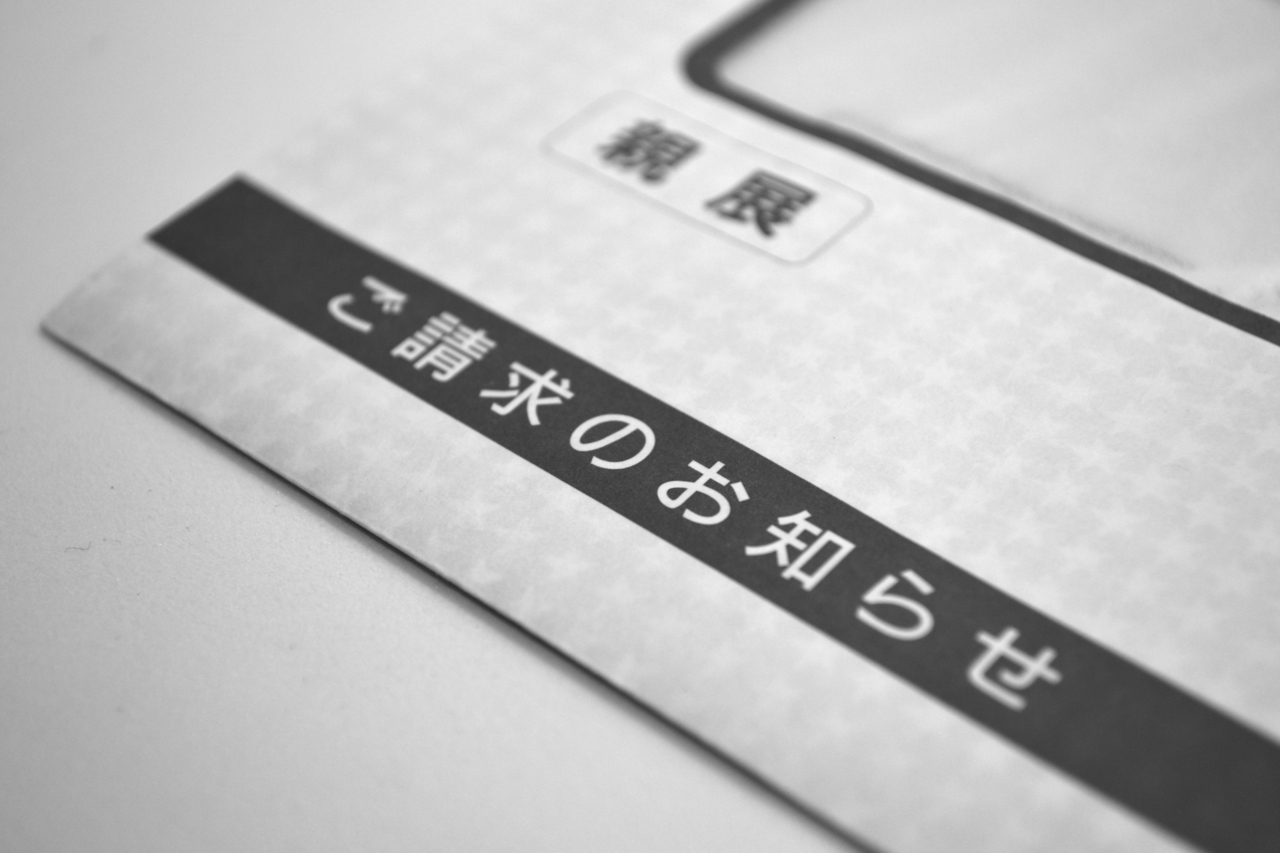
請求書を受け取ったら
項目の確認をしましょう。
インボイスとは、正確な消費税額や適用税率を伝えるための手段です。「このインボイスを発行した事業者は正しく登録されています」「この取引で預かった消費税は○○円になります」という情報を売る側から買う側に正しく伝える役割を担っています。
インボイスに記載しないといけない項目は以下の8項目になります。
1.請求書発行事業者の氏名または名称
2.取引年月日
3.取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
4.税率ごとに区分して合計した対価の額
5.書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
6.適格請求書発行事業者の登録番号
7.適用税率
8.消費税額
1~5までの項目はすでに記載されているため、インボイス制度では6~8までの項目を追加することになります。
インボイスでなければ仕入税額控除できない!?

制度が始まってから6年間は
経過措置があります。
インボイス制度では、仕入先からインボイスをもらわなかったら、仕入税額控除できないというルールになります。
消費税の納税のしくみは、「預かった消費税」から「支払った消費税」を差し引いて、納める消費税を求めますが、「支払った消費税」を差し引くこと「仕入税額控除」といいます。
インボイス発行事業者に登録していない事業者からの請求書や領収書は、インボイスでないため、買い手側は仕入税額控除ができません。
そのため消費税の納税額が多くなるのです。
インボイス制度によって影響を受ける事業のために以下の経過措置があります。
①令和5年9月30日までは免税事業者からの仕入れであっても仕入控除ができます。
②令和5年10月1日から令和8年9月30日までは80%控除の経過措置があります。
③令和8年10月1日から令和11年9月30日までは50%控除の経過措置があります。
インボイスの登録制度について

登録申請手続きはe-taxで完結できます。
インボイスを発行するには、税務署のインボイス発行事業者の登録簿に登録される必要があります。
◆インボイス発行業者の登録の流れ
①登録申請書の提出
②税務署による審査
③登録及び公表・登録簿への登載
④税務署からの通知
発行されたインボイスが正しくないと、仕入税額控除ができません。
インボイス発行業者の登録内容が国税庁のホームページで公表することによって、インボイスの発行事業者がきちんと登録されているかを確認することができます。
免税事業者は消費税を納税してなく、消費税額を伝える必要がないのでインボイス発行事業者の登録ができません。しかし、免税事業者でも『課税事業者選択』という制度を使って課税事業者になることで、インボイス発行事業者の登録ができるようになります。免税事業者が令和5年(2023年)10月1日を含む事業年度からインボイス発行事業者になる場合は、期間限定の特例があり、インボイス発行事業者の登録申請のみを提出すればよいことになっています。
インボイス制度ページのご紹介
下記のページもぜひご一読ください。

国税庁の動画は講義形式でわかりやすく説明してくれてます。
新着情報・お知らせ
「事務所news01月号」をアップしました。
「事務所news12月号」をアップしました。
「事務所news11月号」をアップしました。
税理士法人ASHA(アサ)
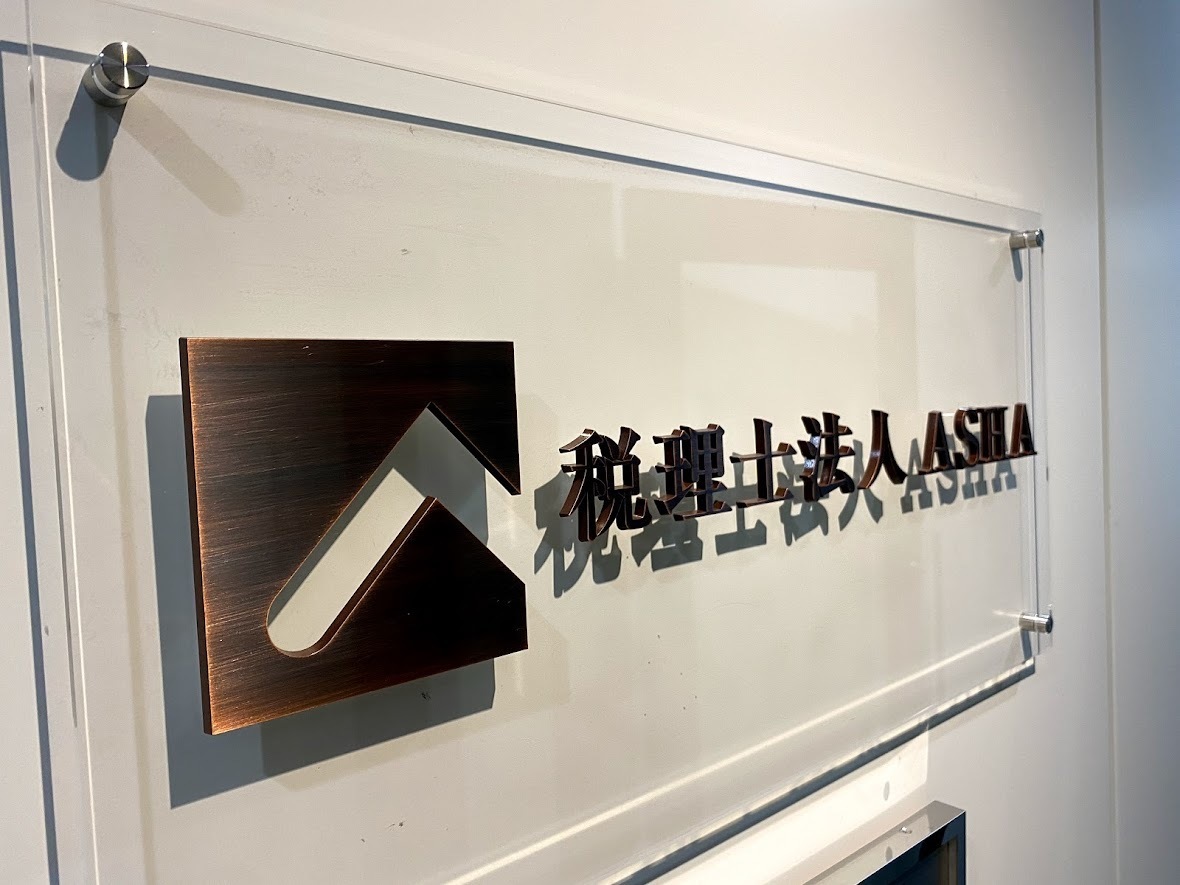
住所
〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町1-2-15
第3朝日ビル7階
アクセス
小伝馬町駅・人形町駅徒歩5分、
三越前駅徒歩7分、
新日本橋駅徒歩6分
受付時間
9:30~17:30
定休日
土曜・日曜・祝日

